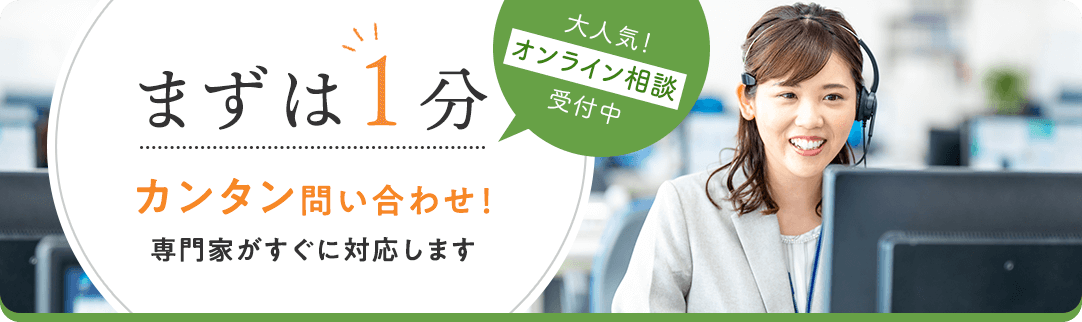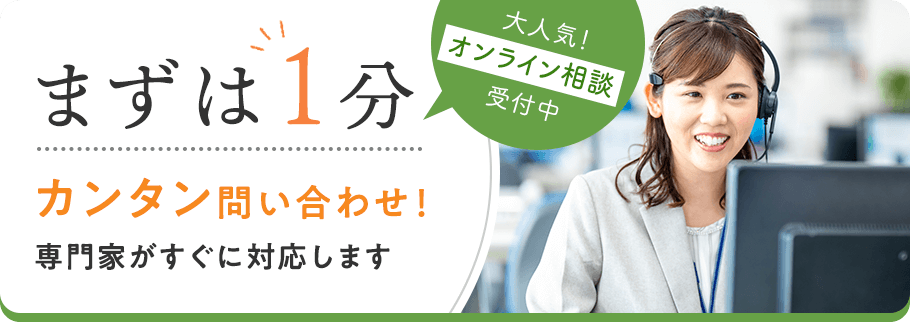相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点
公開日:2021.02.19 更新日:2021.02.23

■ この記事で解説すること
相続放棄とは
そもそも相続とは、亡くなった方(=被相続人)が遺した遺産を、相続すること(=受け取ること)です。
相続放棄とは、相続する権利がある人が「その権利を放棄すること」です。
例えば、「被相続人に借金があり、プラスの遺産を大きく上回る場合」などは、相続放棄の検討をされる方は少なくありません。
ただし、相続放棄には期限や注意点があります。
安易に相続放棄を決断する前に、一度チェックしてみてください。
そもそも相続の対象にならないもの
まず、被相続人が遺したものすべてが相続の対象になる訳ではありません。
下記に挙げるものは、相続放棄の際に検討しなくて良いものとなります。
生命保険
生命保険は相続の対象とはなりません。
生命保険金は、契約者と保険会社との契約により、契約者が保険会社に対して支払った保険料の対価として支払われるものだからです。
したがって、相続放棄をした場合も、受け取ることができます。
一身専属的な権利・義務
生活保護の需給や、年金の受給、国家資格、SNSのアカウントなどです。
これらは、一般的には引き継ぐことや相続することができません。
相続放棄の手続き方法と、手続きにかかる期間
相続放棄の手続きは「3ヶ月以内」に
まず相続放棄自体は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。
正確には、被相続人が亡くなり「自分が相続人になったことを知ってから」3か月以内です。
つまり、被相続人が亡くなったことを知らされなかった場合などは、3か月を超えての相続放棄も可能となるケースがあります。
相続放棄の手続き方法と期間
必要書類を用意し、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。
相続手続き 必要な書類の一覧
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本…etc
書類の提出から約20日~30日で手続きが完了します。
書類提出後は、相続放棄の意思確認があり、その後相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄の前に、マイナスの遺産を正確に調査
相続放棄にあたり、被相続人が遺した遺産を放棄するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
後悔のない判断のために、まずは被相続人がどんなものを遺したかを「正確に知る」ことを心がけましょう。
特に借金などのマイナスの遺産に関しては、周囲には隠していることが少なくありません。
それではマイナスの遺産を把握するにはどうしたらよいでしょうか。
全国には下記の3つの信用情報機関があります。
これらに信用情報を開示請求すれば、大方の借金などは発見できます。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
メガバンク、ネット銀行、地方銀行などのほか、信用金庫やろうきんなどの信用情報を取り扱っています。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)
主に消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)で登録された信用情報を取り扱っています。
JICC(株式会社日本信用情報機構)
消費者金融や銀行(主にネット銀行、地方銀行など)の信用情報を取り扱っています。
これらは基本的に他人のものを確認することはできませんが、相続人であることが証明できれば、開示請求が可能です。
請求から、約7日~10日で結果が返ってきます。
ただし、個人間のお金の貸し借りや闇金、または借金の保証人になっているかどうかまではわからない場合がありますので、注意が必要になります。
また、被相続人宛の郵便物や通帳の履歴や振込伝票の控えなどを確認することで発覚するようなケースもあります。
相続放棄のほかに「限定承認」がある
基本的に相続は、プラスの遺産もマイナスの遺産あわせて「どちらも相続する」か「どちらも相続放棄する」かを選択する必要があります。
しかし、例外的な措置が「限定承認」です。
限定承認とは
「限定承認」とは、プラスの遺産をすべて相続し、マイナスの遺産は一切相続しないという、都合の良いものではありません。
相続したプラスの遺産の範囲で、マイナスの遺産を相続するというものです。
例えば100万円のプラスの遺産と、1,000万円のマイナスの遺産があった場合を仮定します。
通常の相続では「どちらも無制限に相続する」か「どちらもすべて放棄する」かの2択です。
このとき「限定承認」を選択した場合は、100万円のプラスの遺産の範囲内で、マイナスの遺産を負担することになります。
したがって、たとえ債務が超過していた場合でも責任の範囲は取得した遺産の範囲に限られるので、自己の固有財産から負担をする、すなわち「持ち出しをする」必要がありません。
もちろんプラスの遺産の方が多ければ残った財産は所得することが可能になります。
例えば、「マイナスの遺産が多いが、実家などの愛着のある不動産や事業などは承継したい」場合や「どれだけマイナスの遺産があるか図り知れず、後から多額の借金が発覚したら怖い」という場合には限定承認を検討する価値があります。
ちなみに、相続人が複数の場合、相続放棄は1人でもできますが、限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があります。
相続放棄ができない よくある場合4選
相続放棄ができない場合① 自分が連帯保証人になっている場合
被相続人の借金において、相続する方本人が連帯保証人になっている場合は、たとえ相続放棄をしたとしても連帯保証人として借金の返済をしなければならない立場は変わりません。
連帯保証債務は相続債務とは別個の債務だからです。
相続放棄ができない場合② 被相続人の遺産を処分してしまった
被相続人の所有物を処分してしまうと、「相続を承認した」とみなされてしまうことがあります。
土地や建物、株式などの高額なものに限らず、衣類やアクセサリーなどの小物まで、対象は様々です。
相続放棄をする際には、安易に被相続人の所有物を処分しないことがオススメです。
相続放棄ができない場合③ 被相続人の借金の返済をしてしまった
被相続人が亡くなった後、突然借金の取り立てが自分に来るケースも稀にあり、動揺して一部の返済をしてしまう方も少なくありません。
しかし、ほんの一部でも返済してしまうと、「相続の意思がある」と判断され、マイナスの遺産をすべて被ることになりかねません。
そのため、相続する気のない被相続人の借金は、一部でも返済してはいけません。
また、その場をしのぐために、返済するという発言も控えた方が良いでしょう。
相続放棄ができない場合④ 相続放棄の期限3か月を超えた場合
基本的には3か月以内に、相続放棄の手続きをする必要性は前述の通りです。
もちろん、「特別な事情があり、3か月以内に決断できない」場合には家庭裁判所に対し熟慮期間伸張の申し立てをすることや、「相続することを決断するにはしたが、判断を誤るに相当な理由があると認められた」場合には、3か月を経過しても、相続放棄が認められるケースもあります。
しかし、基本的には何もしないで3か月を経過すると、相続の意志ありとみなされてしまうため注意が必要です。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄は一度すると熟慮期間中でも撤回することができない
ただ、第三者による詐欺や強迫によって相続放棄をしてしまったときのように、家庭裁判所への申述によって取り消しをすることも一応認められていますが、これはあくまでも例外にすぎません。
例えば、「借金があったので、慌てて相続放棄したが、よく調べたら、借金を大きく上回る資産が見つかった」というケースは意外にも多くあるものです。
そのため、きちんと遺産調査を行った上で、冷静に判断することが重要です。
相続放棄をしたら、次の相続順位の方に相続権が移る
自分が相続放棄した場合、相続範囲の中で、次の方に権利が移ります。
相続の優先順位と、血族の種類は次の通りです。(配偶者は必ず相続できます。)
相続の優先順位
- 第1順位は子および代襲相続人
- 第2順位は両親などの直系尊属
- 第3順位は兄弟姉妹および代襲相続人
そのため、借金があり相続放棄した場合は、次の相続順位の方にもその旨を知らせましょう。
気が付かずに相続してしまうおそれがあり、揉め事になってしまうかもしれません。
相続放棄と同時にプラスの資産も放棄となる
繰り返しになりますが、相続放棄をするということはプラスの遺産も相続できません。
そのため、被相続人との思い出や、何らかのこれからの生活のために絶対に残しておきたいものがある場合は、安易に相続放棄をしてはいけません。
相続放棄は自分でできる?
結論、自分で行うことが可能です。
限定承認と異なり、他の相続人との調整もありません。
ただし、自分で行う際にはいくつか注意が必要です。
注意点1:遺産調査をすべてやりきることができるか
相続放棄をしてから、思わぬプラスの遺産が出てきたとしても、相続放棄を撤回することはできません。
「どんなことがあっても、相続を放棄する」という合意が相続人全員で取れていれば問題ないものの、慎重に検討すべきです。
また、相続放棄さえすればすべての責任から放免されるというわけではありません。
例えば建物など誰も相続する者がいなければいずれは廃墟となってしまいますが、次順位の相続人など管理を引き継ぐ者が現れるまで、自己の財産と同一の注意義務をもって管理を継続する必要がある点に注意が必要です。
注意点2:遺産の価値をきちんと評価できるか
遺産をすべて洗い出すことができても、その価値をきちんと把握できていない場合が考えられます。
「自分が考えていたよりも価値が高かった」ということも起き得ます。
また、プラスの遺産にかかる税金額を考慮して相続放棄する場合も同様です。
専門知識がないが故に、税額計算を誤ってしまったり、もしくは相続税を節約できる有効な手段を見逃したまま、相続放棄を選択されるケースも少なくありません。
司法書士へ相談・依頼すると良いこと・メリット
司法書士に相談することで、多くの時間と労力がかかる財産調査をはじめ、財産の正確な評価、相続放棄に関連する書類作成などの手厚いサポートを受けられます。
さらに「相続放棄という判断自体が適切でない」場合は、アドバイスをすることも可能です。
そのため、相続放棄を視野にいれたタイミングで、一度早めに相談することがおすすめです。
まとめ(花沢事務所 司法書士より)
遺産相続とは亡くなった方が遺してくれた遺産を大切に受け継ぐことでもあります。
もちろん予期せずマイナスの遺産が発覚した場合は、無理に相続する必要は全くありません。
ただし、勘違いや判断ミスによりせっかくのプラスの遺産の価値に気づかずに手放すことは、亡くなった方にとっても、相続人にとっても喜ばしいことではありません。
そのため、多少の時間と労力はかかっても、正しい情報を調べあげ、他の相続人たちと慎重に相談したうえで判断していくことが重要です。
とはいえ、相続放棄の期日は3ヶ月以内と決められているので、迷ったらまずは無料相談サービスを活用してみてください。
「相続放棄の手続き」に関する無料相談会について
「相続放棄の手続き」に関する無料相談会
花沢事務所では、「相続放棄の手続きや注意点」について個別で無料相談会を実施しております。土日対応OK、平日は19時までご相談可能です。お気軽にご連絡ください。
■ 記事監修について

-
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
相談実績は10,000件を突破、各メディアや書籍、セミナー登壇実績も多数あり。各事務所にて無料相談会を実施中です。(平日夜19時まで、土日祝日も相談可能)
■ よく読まれている記事
 終活のはじめかた2021.02.27無効にならない遺言書の書き方や種類、注意点を解説
終活のはじめかた2021.02.27無効にならない遺言書の書き方や種類、注意点を解説 相続の手続きガイド2021.02.24認知症リスクに効果大!家族信託のメリット
相続の手続きガイド2021.02.24認知症リスクに効果大!家族信託のメリット 相続の手続きガイド2021.02.19相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点
相続の手続きガイド2021.02.19相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点 遺産相続ガイド2021.02.16遺産分割協議とは?なぜ必要?書き方や提出の流れを解説
遺産相続ガイド2021.02.16遺産分割協議とは?なぜ必要?書き方や提出の流れを解説