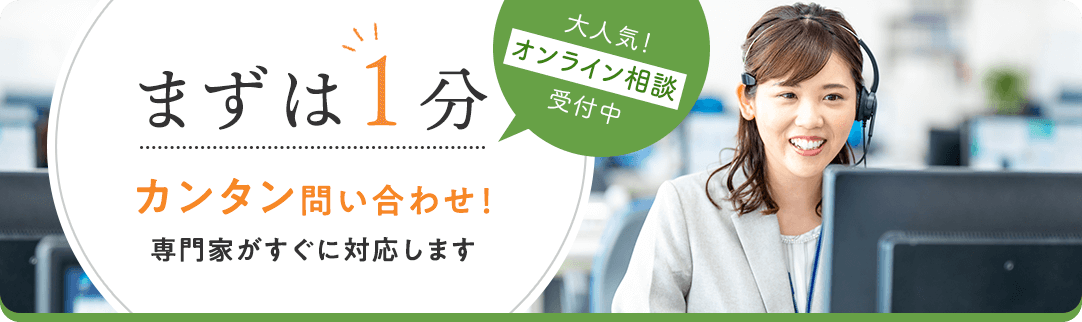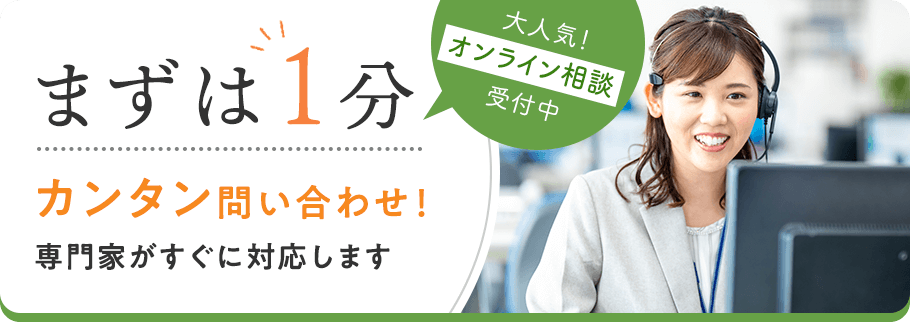二世帯住宅の不動産相続はどうする?不公平な分割にならないための注意点
公開日:2021.02.14 更新日:2021.03.13

■ この記事で解説すること
不相談相続は「不公平」が前提
相続でもめるのは、高額な遺産があるケースだと思われているかもしれませんが、
実際に遺産分割協議で揉めて調停となっている件数の多くは、遺産額が5000万円以下の一般家庭です。
中でも、不動産相続でもめやすい理由のひとつとしては、現実的に分割することが難しいことが挙げられます。
実際に土地を分割することも容易ではありませんし、共有持分のみでは不動産の価値が大きく下がってしまうためです。
では、なぜもめるのでしょうか?
不動産相続で揉めるよくある事例と理由
①不動産を誰が取得するかでもめる
不動産は、現金のように分割できないので、基本的には1人の相続人が単独で取得することになります。
すると、「誰が取得するのか」という問題が起こります。
不動産がひとつしかなく、複数の相続人が取得を望んだ場合はもちろんですが、
1人が取得を望むケースでも、他の相続人との間で相続分の不均衡が起こるため、もめる場合が多いです。
また、たったひとつの不動産が自宅の場合は、
そこに住み続けたい人と、売却・賃貸したい人など、相続人同士で希望が異なるため、もめやすくなります。
②不動産を相続したはいいものの、「代償金の支払」ができなくてもめる
ひとつの不動産を、1人の相続人だけが相続することになると、
その相続人が他の相続人に対して代償金を支払わなければならない場合があります。
相続財産として3000万円の不動産と600万円の預貯金があり、相続人は長男、次男、三男の3人というケースを考えてみましょう。
ケース1:長男が実家を相続、他の兄弟は預貯金を相続した場合
長男
家を相続:3000万円
次男
親の預金:300万円
三男
親の預金:300万円
=>不公平感からもめやすい
ケース2:長男が実家を相続するが、他の兄弟との差額を現金で支払う場合
長男
家を相続3000万円−1800万円=1200万円
次男
親の預金300万円+長男から900万円=1200万円
三男
親の預金300万円+長男から900万円=1200万円
=>長男が支払えない可能性が高い
この場合、もともとの法定相続分は、3人ともそれぞれ1200万円ずつ(3分の1)です。
しかし、長男が3000万円の不動産を相続して、次男と三男が300万円ずつ預貯金を相続するとなると、長男の取り分が他の2人よりも2700万円も高くなります。
この不公平を解消するためには、不動産を相続する長男が、代償金を他の相続人に支払わなければいけません。
長男が弟2人にそれぞれ代償金として900万円払えば、3人ともそれぞれ1200万円ずつとなり、公平になります。
ところが、そもそも代償金の金額をいくらにするかということでもめるケースも多く、長男が代償金の支払をしない(できない)ことで問題が発生するケースも少なくありません。
また、その不動産が実家・自宅であり、長男がもともと親と同居していた場合などには、長男が相続できないと住居を失ってしまうことになります。
③不動産の評価方法でもめる
「誰が相続するか」「代償金がいくらになるか」を決めるために不動産を評価するのですが、その評価方法でもめることが多くあります。
不動産の価格は変動するため、いつの時点を基準にするかで価格が変わるうえ、
実勢価格や相続税路線価、固定資産税評価、路線価など、評価方法によっても評価額が変わります。
さらに、実勢価格は、査定を依頼する業者によって、数百万円以上の差額が発生することもあります。
二世帯住宅の相続はどうなるの?
近年、夫の両親、もしくは妻の両親と、二世帯住宅で同居している人は少なくありません。
二世帯住宅の場合、親世代が亡くなっても、子世代は暮らし続けることができるのでしょうか?
二世帯住宅の相続について考えてみたいと思います。
二世帯住宅の相続 チェックポイント
二世帯住宅の相続は、どのようなルールで行われるのでしょうか?
①不動産相続で重要なのは「誰の名義になっているか」
二世帯住宅が建っている土地と、二世帯住宅の建物自体がすべて父親の名義であれば、父親が亡くなると、土地も建物も遺産相続の対象となります。
また、土地は母親の名義、建物は母親&長男夫婦の3人の共有名義という場合は、母親が亡くなると、土地については相続財産になります。
そして、土地と建物の母親の持ち分も相続財産とみなされ、法定相続人である兄弟達で分け合うことになります。
つまり、二世帯住宅が建っている土地と、二世帯住宅の建物自体がすべて長男夫婦の名義になっていれば、親世代が亡くなっても問題はないということです。
②もしもきょうだいが「不動産をきっちり等分して」と主張したら?
遺産相続は法律で定められた権利です。
二世帯住宅が建っている土地と二世帯住宅の建物自体が親の名義になっており、遺産相続の対象になる場合、相続人の1人が「きっちり等分して」と主張したら、断ることができません。
相応の金額を支払って土地や建物の等分を求める兄弟の持ち分を買い取るか、もしくは売却したお金を等分して分けるか等の手段をとる必要があります。
二世帯住宅で暮らし続ける方法は?
二世帯住宅が建っている土地と二世帯住宅の建物自体が親の名義になっており、遺産相続の対象になる場合、子ども世代が二世帯住宅で暮らし続けるにはどうしたらよいのでしょうか?
対応策をまとめてみました。
①不動産の名義人である親が亡くなった後なら
- 土地と建物以外の相続財産を、ほかのきょうだいに分けてもらい、二世帯住宅は同居していた子どもが相続できるよう話し合う
- ほかのきょうだいに二世帯住宅の親の持分に対する法定相続分に相応する金額を払って納得してもらう
②親が亡くなる前なら
- しっかりしているうちに遺言書をつくってもらう
一方、父親が「土地と建物は長男に相続させる」という遺言を遺してくれたにも関わらず、父親より先に長男が亡くなった場合、
「土地建物は長男に相続させる」という遺言は「無効」になり、無効となった場合は改めて「遺産分割」の対象となります。
つまり、父親の子ども(二男と三男)と孫(長男の子ども達)で分け合うことになるのです。
こうした状況を避けるには、「万が一、〇〇が遺言者よりも先に、もしくは同時に死亡した場合には、当該財産は長男の配偶者△△(あるいは孫××)に遺贈する」といったように、予備的条項を盛り込むという選択肢もあります。
二世帯住宅を生前贈与するとどうなるか?
二世帯住宅を「生前贈与」するとなると、何百万、何千万という贈与税がかかる可能性があります。
「相続時精算課税」などを活用する方法もありますが、相続税の節税対策などで不利になることもあるので、専門家へ必ず相談する必要があります。
また、名義変更の登記のコストも、遺言による相続に比べると割高になります。
不動産登記にかかる「登録免許税」は、相続の場合、不動産評価額0.4%ですが、贈与の場合は不動産評価額の2%です。
例えば不動産評価額が3000万円の場合、相続するときの登録免許税は12万円ですが、贈与では60万円と5倍も高くなります。また、忘れずに翌年の確定申告をしなければいけません。
「どうしても今でなくては!」という場合には、生前贈与も検討の余地があるかもしれませんが、
後悔をしないためにも、司法書士や税理士といった専門家に相談すると安心です。
不動産相続で注意したいこと
不動産を「共有財産」にしない
相続でもめて、遺産分割協議が長引いてくると、つい不動産を相続人全員の共有にしてしまいたくなるかもしれません。
しかし、不動産を複数の相続人で共有相続する際には注意が必要です。
例えば一筆の土地を子3名で3分の1ずつ相続した場合、不動産を売却する際には、子全員の協力が必要となります。
また、自らが相続した3分の1の持分では不動産の価値が大きく下がってしまいます。
そのため、1つの不動産を複数の相続人で持ち合う、「共有状態」は避けたほうが良いでしょう。
不動産は相続人の1人で相続するようにし、不動産以外の財産をその他の相続人が相続するなどの分割が望ましいです。
相続財産が不動産しかなく、その不動産が1人の相続人の自宅ではないのなら、
売却を前提として売買代金を相続人間で分割するという方法も検討すると良いでしょう。
不動産相続で揉めないために
不動産相続に関する遺言書を作成する
相続、遺産分割での不動産のトラブルを防ぐには、遺言を残しておいてもらうことが有効です。
これまでご紹介したトラブルや争いの原因の多くは、遺言がなく、相続人同士で遺産分割協議をして決めるしかないために発生しているものです。
遺言があれば、基本的には遺言に従って相続するため、面倒な遺産分割協議や不動産の評価などをしなくても済みます。
■ 記事監修について

-
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
相談実績は10,000件を突破、各メディアや書籍、セミナー登壇実績も多数あり。各事務所にて無料相談会を実施中です。(平日夜19時まで、土日祝日も相談可能)
■ よく読まれている記事
 終活のはじめかた2021.02.27無効にならない遺言書の書き方や種類、注意点を解説
終活のはじめかた2021.02.27無効にならない遺言書の書き方や種類、注意点を解説 相続の手続きガイド2021.02.24認知症リスクに効果大!家族信託のメリット
相続の手続きガイド2021.02.24認知症リスクに効果大!家族信託のメリット 相続の手続きガイド2021.02.19相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点
相続の手続きガイド2021.02.19相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点 遺産相続ガイド2021.02.16遺産分割協議とは?なぜ必要?書き方や提出の流れを解説
遺産相続ガイド2021.02.16遺産分割協議とは?なぜ必要?書き方や提出の流れを解説