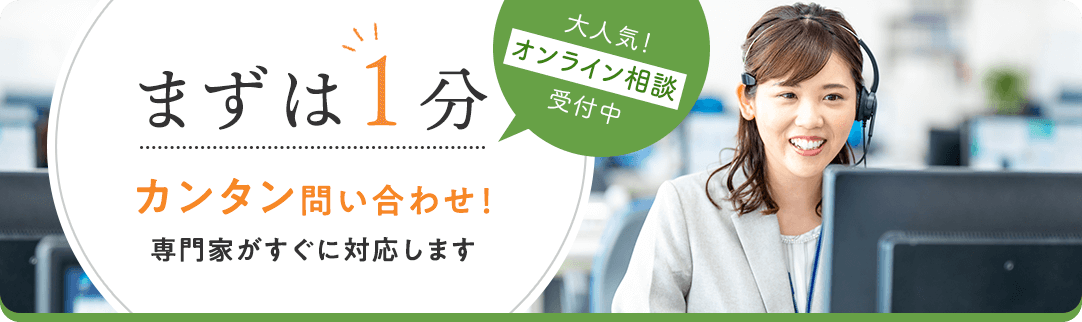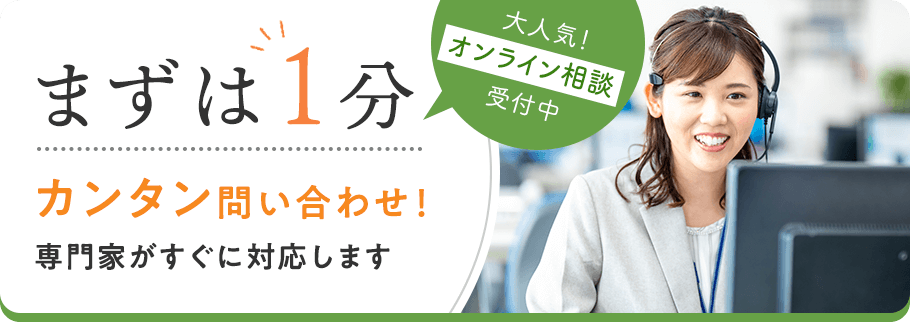「小規模宅地等の特例」が適応される条件まとめ
公開日:2020.11.03 更新日:2021.02.28

■ この記事で解説すること
節税効果バツグン!「小規模宅地等の特例」を逃すな
親が亡くなった場合、子が親の土地を相続するケースは少なくありません。
一方で「相続税」がかかるのは困りもの。
思わぬ負担を強いることに繋がりかねません。
実は、相続の際に「小規模宅地等の特例」が適用されれば、
土地の評価額を大きく下げ、相続税を安くすることが可能なのです。
ここでは、「小規模宅地等の特例」がどんなものなのか、
どんな人が、どんな場合に認められるのかを紹介します。
「小規模宅地等の特例」とは
亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、
一定の要件を満たした人が相続したときに、最大80%節税できる特例です。
「小規模宅地等の特例」のメリット
小規模宅地の特例を使うことができれば、相続した土地の評価額を大きく下げられるので、大幅な節税が期待できます。
「小規模宅地等の特例」の注意点
以下のように「宅地の種類」によって、限度面積や減額割合が異なります。
特例対象宅地が複数ある場合には、最も有利になるように選択しなければなりません。
特定居住用の土地に特例を使うためには
※次にあげる3つのうち1つでも当てはまることが必要です。
- 被相続人の配偶者が土地を相続
- 被相続人と同居していた人が土地を相続
- 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得 ※家なき子特例
特定事業用の土地に特例を使うためには
※次にあげる2つのうち1つでも当てはまることが必要です。
- 相続開始前からその土地で事業をやっている
- 相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う
貸付事業用の土地に特例を使うためには
※次にあげる2つのうち1つでも当てはまることが必要です。
- 相続開始前から土地の貸付を行っている
- 相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている
また、それぞれの土地で特例を使える人、減額される率がちがうので注意が必要です。
節税効果が大きい特例だけに、適用要件が細かく手続きが難解であることが多いです。
たとえ専門家でも、思わぬ勘違いすることがあり、失敗事例も少なくありません。
親や子の生活様態などが関係し、ちょっとしたことで特例が使えなくなる恐れもあります。
これから不動産を購入する予定のある人は、特例の適用に影響がないか、
相続案件の取り扱い実績が多い複数の税理士に相談しておくと安心かもしれません。
「小規模宅地等の特例」を受けられるケース&受けられないケース
特例を受けられるケース
- 親と同居していた家を子が相続した場合
- 親が自宅で一人暮らしで、かつ相続する子どもが賃貸住宅で暮らしている場合
- 相続発生時(死亡時)に親が施設で暮らしていた場合
特例を受けられないケース
特例を適用して評価減を受けた自宅用の土地は、「相続税の申告期限(相続発生の10カ月後)まで所有する」という適用要件があります。
しかしそのことを知らず、申告期限以前に相続した土地を売ってしまい、
特例を受けられなくなってしまうケースがあります。
二世帯住宅で、親と子の居住部分を区分所有で登記している場合、敷地全体についての特例は使えません。
適用範囲は条件により異なりますが、区分所有していた二世帯住宅を、
親と別生計の子が引き継いだ場合、敷地全体に対する特例は使えません。
土地評価が80%減になる「小規模宅地等の特例」
特定の居住用の宅地について
減額割合:80%限度面積:330㎡ ※約100坪まで適用可
特定の事業用の宅地について
減額割合:80%限度面積:430㎡ ※約120坪まで適用可
貸付事業を行なう宅地について
減額割合:50%限度面積:200㎡ ※約60坪まで適用可
まとめ:自宅土地「80%減」が原則認められる条件
特例が使える条件
- ①配偶者への相続なら、同居・別居いずれもOK
- ②親と同居の子が相続し、相続税申告期限まで居住かつ所有すればOK
- ③亡くなった親に配偶者や同居親族がいなければ、別居の子どももOK。
ただし、相続直前3年以上賃貸で、相続後も申告期限までその土地を所有する場合に限る。
■ 記事監修について

-
創業39年、横浜・横須賀・東京丸の内に事務所を構える司法書士事務所です。
相続、遺言、終活、債務整理、不動産登記、会社設立、定款変更、建設業許可申請など、多岐に渡ってサポートを行っております。
相談実績は10,000件を突破、各メディアや書籍、セミナー登壇実績も多数あり。各事務所にて無料相談会を実施中です。(平日夜19時まで、土日祝日も相談可能)
■ よく読まれている記事
 終活のはじめかた2021.02.27無効にならない遺言書の書き方や種類、注意点を解説
終活のはじめかた2021.02.27無効にならない遺言書の書き方や種類、注意点を解説 相続の手続きガイド2021.02.24認知症リスクに効果大!家族信託のメリット
相続の手続きガイド2021.02.24認知症リスクに効果大!家族信託のメリット 相続の手続きガイド2021.02.19相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点
相続の手続きガイド2021.02.19相続放棄の手続きは期限がある?よくあるミス事例や注意点 遺産相続ガイド2021.02.16遺産分割協議とは?なぜ必要?書き方や提出の流れを解説
遺産相続ガイド2021.02.16遺産分割協議とは?なぜ必要?書き方や提出の流れを解説